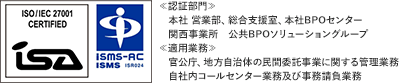その不調は自律神経が原因かも?自律神経の整え方を知ろう
- お役立ち情報
はじめに
「風邪でもないのに、体がだるい」「なんとなく疲れが取れない」そんな時は、自律神経の乱れが影響しているのかもしれません。自律神経は、気温や気圧、ストレス、ホルモンバランスなど、様々な要因で乱れていきます。自律神経が乱れると「眠れない」「疲れやすい」「やる気が出ない」「頭痛がする」などの不調が生じやすくなり、仕事に影響を与えてしまうことも少なくありません。
そこで今回は、自律神経の乱れによる不調を予防・改善するために、日常生活に取り入れやすい自律神経の整え方についてご紹介します。
そもそも自律神経とは?
自律神経は、脳に酸素と栄養を供給するための装置であり、24時間休むことなく働いて、体内を常にベストな状態に保ち続ける神経です。
自律神経は「交感神経」と「副交感神経」の二つに分けられ、交感神経はアクセル(活動モード)の役割、副交感神経はブレーキ(リラックスモード)の役割があります。この二つの神経がバランスを取り合うことで、健全な日常生活を送ることができます。
ところが、食生活の乱れ、不規則な生活リズム、過度なストレスなどにより自律神経のバランスが崩れると「やる気が出ない」「眠れない」「頭痛がする」といった、様々な不調があらわれやすくなります。
自律神経が乱れるとどんな症状が出るの?
自律神経のバランスが崩れると、次のような症状があらわれます。
【身体的症状】
・頭痛やめまい、立ちくらみが起こる
・慢性的な肩こり、腰痛
・手足が震える、しびれる
・のどがつまる感じがする
・全身がだるい
・動悸、息切れがする
・ほてりや冷えを感じやすい
・下痢や便秘になりやすい
・よく眠れない
【精神的症状】
・なんとなく不安になる、イライラする
・わけもなく憂うつな気分になり、落ち込む事がある
・物事に興味、関心がなくなる
・やる気が出ない
・集中力がなくなる
・物事がなかなか決断できない
自律神経が乱れる原因
自律神経が乱れる主な原因は、ストレス、不規則な生活、加齢、疾患などです。転職や新生活、引越しなどの環境変化や、仕事のプレッシャー、人間関係によるストレス、寒暖差、気圧や湿度の変化といった、身体的・精神的なストレスの蓄積により乱れやすくなります。
また、暴飲暴食・運動不足・睡眠不足などの生活習慣の乱れ、月経や排卵などによるホルモンバランスの乱れも、自律神経のバランスを崩す要因になります。
自律神経を整えるコツ ~1日の過ごし方編~

自律神経を整えるためには、生活リズムを整え、日頃からストレスを溜めないよう心がけていく事が大切です。ここでは、自律神経が整う1日の過ごし方についてご紹介します。できるところから、日常生活に取り入れてみましょう。
【朝】
・朝日を浴びる
朝は睡眠中に優位になっていた副交感神経と交感神経入れ替わるタイミングです。朝に太陽の光を浴びることで体内時計がリセットされ、体のスイッチがONモードに切り替わります。
・コップ一杯の水を飲む
起床後にコップ1杯の水を飲むことで、腸が刺激され食べ物を受け入れる準備が整い、朝食の消化吸収力が高まります。水を飲む際は、身体を冷やさないよう、なるべく常温の水にすることが好ましいです。
・朝食を食べる
朝食を食べると、睡眠中に低下した体温が上昇します。体温が上昇すると、交感神経が優位になり、活動モードに切り替わります。忙しいからといって朝食を抜くと、なかなか活動モードに切り替わらず、やる気が出なかったり、集中力が続かなくなってしまうため、朝食は少量でもなるべく食べるようにしましょう。
また、朝食はタンパク質と炭水化物を一緒に摂取することがおすすめです。栄養バランスよく摂取することで、代謝が上がり、1日を活動的に過ごす事ができます。
【昼】
・決まった時間に昼食を食べる
昼食をなるべく決まった時間に食べることで、体内時計のリズムが整います。食事の際は、ゆっくりよく噛んで食べ、腹八分目を意識するようにしましょう。よく噛むことで、自律神経を整えるホルモンである「セロトニン」の分泌が促され、リラックス効果が期待できます。
・長時間の同じ姿勢は避ける
デスクワークなどで長時間同じ姿勢が続くと、血行が悪くなり自律神経のバランスが乱れる原因につながります。移動の際はなるべく階段を使う、1時間に1回程度は首や肩回しをするなど、こまめに体を動かして、血流が悪くならないように心がけましょう。
・軽く昼寝をする
適度な昼寝は、自律神経を整えるのに効果的です。昼寝をすることで副交感神経が働き、心身をリラックスした状態に導くことができます。注意したいのは、長時間寝ないようにすること。日中に長時間寝てしまうと、夜に眠れなくなったり、寝つきが悪くなる可能性があるため、昼寝の時間は15分~30分程度にしましょう。
【夜】
・夕食は寝る2時間前までに済ませる
消化の良いものを中心に、寝る時間の2時間前までに夕食を済ませましょう。夕食の時間が遅くなりそうな場合には、スープやおかゆといった胃に負担の少ないメニューにするようにしましょう。
・ぬるめの湯船に浸かる
副交感神経を高めリラックスするためには、寝る1時間前を目安に、ぬるめの湯(38℃~40℃)に20分程度つかることがおすすめです。42℃以上の熱いお湯に短時間つかったり、シャワーのみで済ませてしまうと、反対に交感神経が高まってしまうため、寝る前の入浴方法としては控えた方がよいです。
また、ぬるめの湯であっても、長時間湯船につかりすぎると、汗をかきすぎたり、脱水症状になる可能性があるので注意しましょう。
・ストレッチを行う
深い呼吸とともにストレッチを行うことで、全身の血液循環が高まり、睡眠の質改善につながります。肩こりや首こりの改善、ストレスの緩和など、全身の疲労回復が期待でき、翌日もスッキリと目覚めることができるでしょう。
体が温まっているお風呂上がりに行ったり、ラベンダーなどアロマの香りを嗅ぎながら行うと、リラックス効果が高まります。
・寝る前はスマホを見ない&照明を落とす
スマホやタブレット、テレビ、蛍光灯などの光は交感神経を刺激するため、寝る前のリラックスモードには適していません。理想は寝る2時間前にはスマホやタブレットは見ないようにすること。また、寝室の照明は間接照明に切り替えると、心身がリラックスモードに入りやすくなります。
自律神経を整えるコツ~食べ物編~

自律神経を整えるには、栄養バランスのとれた食事を、毎日なるべく同じ時間帯にとる事が大切です。ここでは、自律神経を整えるために積極的に摂りたい栄養素とそれらを含む代表的な食べ物をご紹介します。
■GABA(ギャバ)
GABA(γ‐アミノ酸)はアミノ酸の一種で、神経伝達物質としてはたらきます。神経の興奮を抑える作用があり、リラックス効果が期待できるため、睡眠の質を高める事ができます。
GABAは穀物や野菜・果物に含まれており、バランスの良い食生活を送っていれば不足の心配はありません。ただし、肉中心の食生活の場合には、意識して摂り入れるようにしましょう。
<GABAを含む食材の例>
・発芽玄米
・米
・じゃがいも
・トマト
・かぼちゃ
・大豆
・キムチ など
■動物性タンパク質
タンパク質は3大栄養素の一つで、自律神経を整えるために必要なホルモンを作る材料となります。特に動物性タンパク質は、食事からしか得られない必須アミノ酸が豊富に含まれているため、不足しないように積極的に摂取しましょう。
<動物性タンパク質を含む食材>
・肉類
・魚介類
・卵
・乳製品(牛乳・チーズなど)
■トリプトファン
トリプトファンは体内では合成されないため、食事によって摂取する必要があります。必須アミノ酸の一つであるトリプトファンは「幸せホルモン」と呼ばれる「セロトニン」を生成する材料となります。セロトニンは自律神経のバランスを整える作用があり、精神を落ち着かせ、リラックス効果をもたらします。脳内でセロトニンが不足すると、攻撃的になり、不安やうつといった症状が出やすくなるほか、睡眠障害をもたらすことがあります。
また、セロトニンの合成にはトリプトファンと合わせてビタミンB6が必要となるため、合わせて摂取するのがベストです。
<トリプトファンを含む食材の例>
・乳製品(牛乳・チーズ・ヨーグルトなど)
・大豆製品(納豆・豆腐・きな粉など)
・卵
・赤身魚(マグロ・カツオなど)
・バナナ
・ナッツ類(アーモンド、カシューナッツ、クルミ、ピスタチオなど)など
■ビタミンB6
ビタミンB6は、脳内の神経伝達物質(セロトニン、ドーパミン、アドレナリンなど)の合成を促進する作用があります。トリプトファンと一緒に摂取することで、脳内にセロトニンの増加が期待できます。
<ビタミンB6を含む食材の例>
・赤身魚(マグロ・カツオなど)
・レバー
・赤身肉(ヒレ肉)
・鮭
・バナナ
・玄米
・ごま など
■ビタミンC
ビタミンCは、野菜や果物に多く含まれる栄養素です。体内で合成ができない栄養素のため、意識して摂取することが大切です。ビタミンCは、ストレス消費されやすく、不足すると疲れやすくなります。
なお、ビタミンCは水に溶けやすく、熱に弱い性質があるため、調理時には水につけすぎない、加熱しすぎないように注意しましょう。
<ビタミンCを含む食材の例>
・パプリカ(赤)
・キャベツ
・ブロッコリー
・サツマイモ
・じゃがいも
・キウイフルーツ
・いちご
・みかん など
■食物繊維
食物繊維には、便のカサを増やし便通の改善を図る、腸内の環境を整えるなどの整腸作用が期待できます。脳と腸は互いに情報交換をしており、腸内環境が悪化すると、その情報が脳に伝わって自律神経が乱れ、心身に様々な不調をもたらします。
食物繊維を摂取して、腸内環境を整え、自律神経のバランスを保つように心がけましょう。
<食物繊維を含む食材>
・こんにゃく
・海藻類(昆布、わかめ、めかぶなど)
・きのこ類
・サツマイモ
・ごぼう
・ブロッコリー
・穀物(玄米、大豆、大麦)など
自律神経を整えるコツ~手のツボ編~

ここでは自律神経を整えるために効果的なツボのご紹介をします。仕事の合間や移動時間などにできる簡単なセルフケアとなりますので、ぜひ参考にしてみてください。
■手のツボ
・合谷(ごうこく)
手の甲側の、親指と人差し指の分かれ目にある「合谷(ごうこく)」は、さまざまな症状に効能がある万能のツボです。自律神経の乱れからくる肩こりやストレスの緩和、頭痛、目の痛みなどを軽減する効果があります。
親指と人差し指が交差する部分から、人差し指側に押していくと、副交感神経が優位になり気持ちが落ち着きます。
・内関(ないかん)
手首のシワから指3本くらい下、細い腱が二本並んでいるところの間にあるのが「内関(ないかん)」です。
精神を安定させる効果があるといわれており、イライラや不安などの気持ちが落ち着きます。また、消化器系の不調にも効果があると言われており、ストレスによる胃の痛みや二日酔いにもおすすめのツボです。
・労宮(ろうきゅう)
労宮は手を握ったときに、手のひらの真ん中(中指と薬指の間の部分)あたりにあるツボです。労宮の労は、疲労や過労の労で、心労や疲労が集まる場所、という意味があります。ストレスや不眠、緊張、不安といった症状に効果があるといわれています。
自律神経を整えるコツ~頭・首・顔のツボ編~

■頭のツボ
・百会(ひゃくえ)
「百のツボがであう」の意味を持つ百会(ひゃくえ)は、頭頂部の真ん中にある少し凹みがある部分にあるツボです。副交感神経を優位にさせる働きを持っており、頭痛や肩こり、目の疲れ、ストレス緩和などに効果があると言われています。
■首のツボ
・天柱(てんちゅう)
首の後ろ側にある「天柱(てんちゅう)」は、自律神経を整えるだけではなく、肩こり、頭痛、眼精疲労、めまい、冷えにも効果的なツボです。天柱を押すと頭の血行が良くなるので、頭重感や疲れがたまってぼんやりしているときに押すと、頭がスッキリします。位置は、首の後ろ、髪の生え際にある中央のくぼみから左右に触れる太い筋肉の外側にツボがあります。
■顔のツボ
・太陽(たいよう)
こめかみに人差し指をあてて指をそろえた状態で、中指辺りにあたるくぼみが太陽のツボです。目の周辺の血流改善に効果的で、ドライアイ、めまい、肩こりからくる緊張性頭痛、目の疲労回復に効果が期待できます。
終わりに
自律神経は、気温や気圧の変化、仕事や人間関係のストレス、不規則な生活習慣などによって乱れやすくなります。
自律神経は自分の意思ではコントロールができませんが、日頃から生活習慣を見直したり、栄養バランスを気にかけた食生活を送ることで、自律神経の乱れを予防・改善することは可能です。できる限り毎日規則正しい生活を送り、イキイキとした日常が過ごせるように心がけていきましょう。