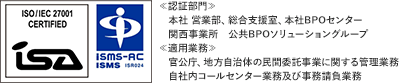多くの人がやっている!?ふるさと納税の仕組みやポイントまとめました!
- お役立ち情報
はじめに
年末になるとCMでもよく流れる「ふるさと納税」。こちらの制度を使用している方も多いでしょう。
聞いたことはあるけど、「よく制度がわからない」、「手続きが面倒くさそう」とまだやったことがない方もいますよね。
本コラムでは今一度ふるさと納税の仕組みや、ポイントをお伝えします。
-
【参考】総務省 ふるさと納税ポータルサイト
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/
ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、納税という言葉がついていますが、実際には自治体への「寄附」のことです。
生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができ、あなた自身で寄付金の使い道を指定できる制度です。
ふるさと納税にて自治体に寄附をした場合、地域の名産品などのお礼の品がもらえ、確定申告を行うことでその寄附金額の一部が所得税、及び住民税から控除されます。
ふるさと納税のメリット・デメリットを理解しよう

総務省のデータを見ると、ふるさと納税は利用者・利用額ともに、年々増加の傾向にあります。
なぜ始める方が多いのでしょうか?
ふるさと納税を利用するメリット・デメリットについて解説していきます。
【ふるさと納税のメリット】
(1)地域貢献ができる
通常であれば自分が住んでいる地域に納税することが基本ですが、
ふるさと納税を活用すると、応援したい地域や生まれた故郷に寄付することができます。
寄付金は地域の公共事業や福祉・教育などに使われ、地域発展に寄与することができます。
(2)税金控除がある
寄付金額に応じて所得税や住民税が控除されます。
控除額は寄付金額から2,000円を差し引いた金額です。
つまり実質的な負担は2,000円のみで、返礼品を受けとることができます。
(全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限があります)
(3)多様な返礼品がもらえる
各自治体は寄付者に対して様々な返礼品を提供しています。
高級食材や工芸品・宿泊券・体験型のサービスなど、多岐にわたる選択肢があります。
【ふるさと納税のデメリット】
(1)控除限度額を超えると自己負担になる
控除される額には上限があります。控除上限額は収入や家族構成、住宅ローンの有無で変動します。
上限額を超えて寄付した場合、超過分は自己負担となり、ふるさと納税のメリットが失われてしまいます。
シミュレーションツールなどを利用し、控除上限額を超えない範囲でふるさと納税を行いましょう。
(2)確定申告が必要になる場合がある
所得税の還付や住民税の控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
ふるさと納税にはこうした税制控除の手続きを簡単に済ませることができる「ワンストップ特例制度」というものがあります。ただし利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
・確定申告が不要な給与所得者である
・年間の寄付先が5自治体以下
「面倒な確定申告はやりたくない」という人は、寄付する自治体の数に気をつけましょう。
また給与所得者でも、住宅ローン控除や医療費控除のために確定申告をする場合は、
寄付先が5自治体以下でも確定申告をしなければならないので注意しましょう。
-
【参照】総務省-ふるさと納税に関する現況調査結果
https://www.soumu.go.jp/main_content/000897133.pdf
ふるさと納税はしないほうがいい人もいる!?
収入や就業条件によっては、ふるさと納税を利用しても得られるメリットが少なくなる場合があります。
とくに下記に該当する人は、損をしてしまう場合があるので利用すべきか慎重に考える必要があります。
●所得税・住民税を納めていない方
専業主婦や扶養内でのパート勤めの方は、所得税・住民税を納めていないのでふるさと納税を利用しても、控除は適用されません。
全額寄附という扱いになってしまいますので、注意が必要です。
●年収が一定の水準を超えない方
年収が低い場合、自己負担金の2,000円を下回る可能性が高く、損をしてしまう場合があります。
総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」によると、給与収入300万円の共働きで、大学生と高校生の子どもがいる世帯では、寄付限度額は7,000円となります。この金額だと返礼品は2,100円以下となり、自己負担額の2,000円より100円多いだけです。寄付をしてもメリットはほとんどなくなってしまいます。
また各自治体が用意している返礼品は、寄付額が5,000円以上の場合が多く、寄付できる限度額が低いと、選べる返礼品も少なくなってしまうのが現状です。
●手持ち資金に余裕がない方
ふるさと納税の税金控除がされるのは翌年であり、分かりやすくいえば『税金の前払い制度』になります。
そのため、現時点で手持ち資金に余裕がない方は、無理して利用しない方が良いかもしれません。
●ふるさと納税をした年に退職する人
仕事を辞めると収入が減るため、翌年の税金が今までよりも少なくなりがちです。
退職した年の収入によっては、ふるさと納税を利用するメリットがない場合も出てきます。
また、退職金を受け取る人も注意が必要です。じつは退職金には優遇措置として退職所得控除というモノがあります。
この優遇措置が適用されれば、翌年の税金はそこまで多額にはなりません。
間違えて限度額を超えた分の金額を寄附することがないよう、十分注意してください。
-
【参考】ふるなび 「ふるさと納税が利用できない人は?しない方が良い人の特徴も徹底解説」
https://furunavi.jp/discovery/knowledge/202409-people_who_cannot/?srsltid=AfmBOop6vc7zh76yfPUXttm2zQWAhqCIcTRD2XuQCMr7YbkkqRhAfXuK
ふるさと納税を行う4ステップ
【STEP1:ふるさと納税ポータルサイトに登録する】
ふるさと納税は楽天やさとふる、ふるさとチョイスなどのポータルサイトを経由して行います。
泉佐野市のように自治体が運営しているサイトを利用できる場合もあります。
【STEP2:控除上限額を確認する】
ふるさと納税で得られる税額控除は、本人の給与収入や家族構成、その他の控除額に応じた上限額があります。
控除上限額を超えて納税すると、自己負担分が増えてしまうので、まずは自分の控除上限額を確認することが大切です。
なお、一定以下の年収で、所得税・住民税がかかっていない人は、そもそも税額控除が受けられません。
控除上限額の目安は総務省のホームページやふるさと納税ポータルサイトで計算できます。
【STEP3:寄付の手続きを行う】
自治体のふるさと納税情報を検索して、寄付したい自治体や返礼品を選択しましょう。
ふるさと納税を行う自治体のうち、97%以上の自治体では、寄付金の使い道を寄付者が選択できるようになっています。
応援したい分野や事業がある場合は、寄付金の使い道から自治体を選ぶのもおすすめです。
寄付したい自治体や返礼品が決まったら、自治体のホームページや、ふるさと納税を取扱うサイトで申込みます。
寄付できる自治体の数に上限はありませんが、寄付先が6自治体以上となった場合にはワンストップ特例制度が使えなくなるので注意が必要です。インターネットで手続きした場合は、寄付金受領証明書が郵送で送られてきます。寄付金受領証明書は、寄付したことを証明した書類になるもので、確定申告する場合に必要です。大切に保管しておきましょう。
【STEP4:税額控除の手続きをする】
ふるさと納税をした年の1月~12月の間に寄付をした分については、締切り(通常、翌年1月10日頃)までに税金控除の申請を完了している必要があります。税金控除の申請には2つの方法があります。
(1)ワンストップ特例制度
ふるさと納税の寄付金控除を、確定申告なしで受けられる制度です。
「ふるさと納税で寄付したい自治体が5つ以下」「ほかに確定申告する必要がない」場合はワンストップ特例制度の利用が便利です。
ワンストップ特例制度を利用する場合、寄付を行った回数だけ申請が必要になります。
同一自治体に2回寄付した場合には、申請は2回必要になりますので注意が必要です。
(2)確定申告
1月1日から12月31日までの1年間の所得と、それに対する所得税を計算し、精算する手続きです。
申告期間は翌年の2月16日から3月15日までとなっています。(※期間の開始日・最終日が土日にあたる場合は、翌営業日が開始日・最終日になります。)
ふるさと納税による税額控除を受ける場合は、その期間中に寄付を証明する書類(受領書)を添付しての申告が必要です。
ただし、確定申告した場合はワンストップ特例制度を利用できなくなるため注意しましょう。
終わりに

「返礼品がもらえる」からふるさと納税を行っているという方もいらっしゃるでしょう。
しかしふるさと納税を利用すると、自身の住んでいる地域では減収につながってしまうことになります。
そのためにも「生まれ故郷、お世話になった地域や応援したい地域への力になる」という、ふるさと納税の趣旨を理解し、活用することが大切です。
メリット・デメリットを理解したうえでふるさと納税を行うか判断していただければ幸いです。
-
セゾンパーソナルプラスのお仕事検索はコチラ
https://www.saison-psp.co.jp/saisonpsp/all/KUJ_1_20_DUD%2CID/CLlist.htm#multiple-form-1